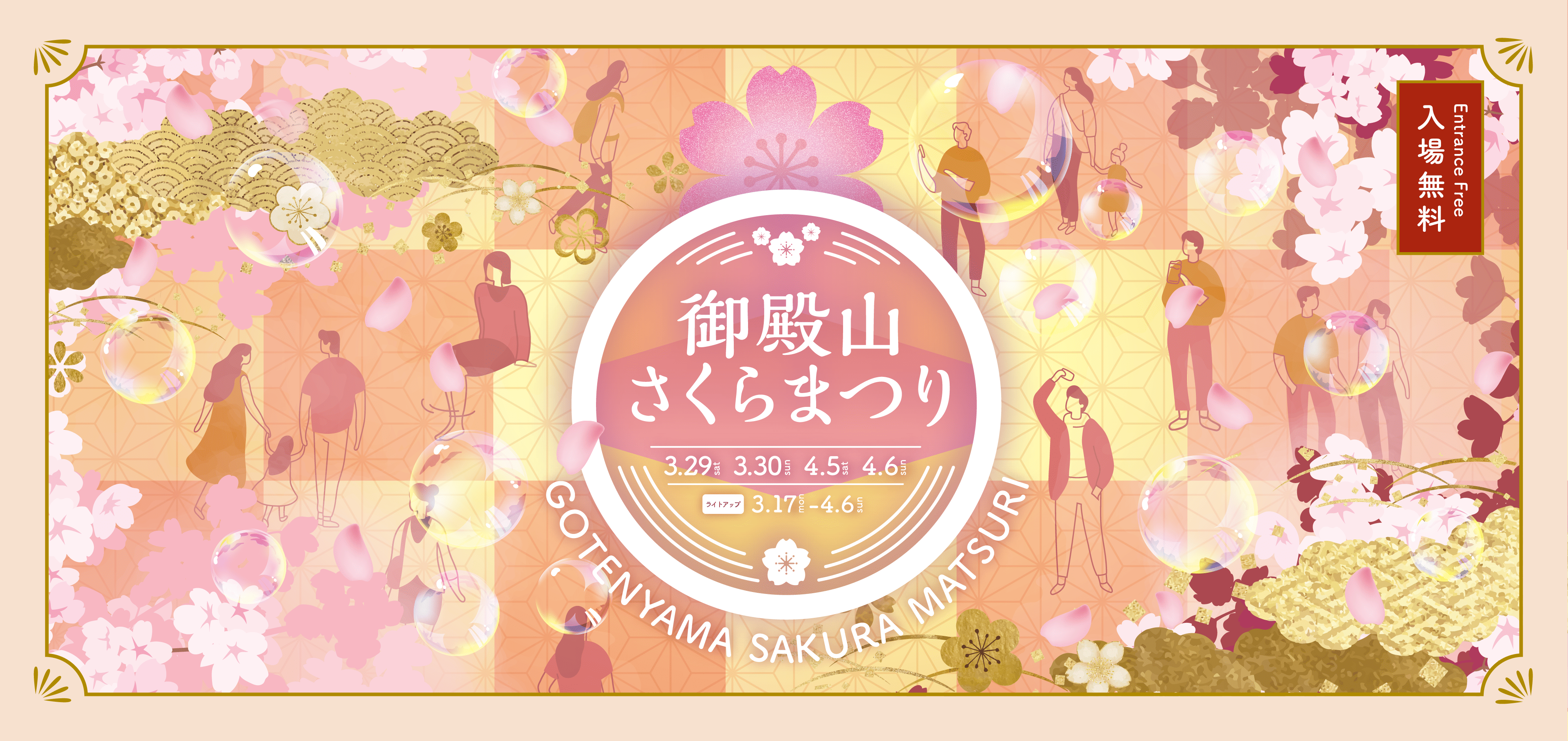大森と聞いてイメージするのは、最近の賑やかな街並みばかりでなく、その歴史にかかわる貝塚、海苔問屋、平和島、山王の邸宅街、馬込文士村などのいずれかだと言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。大森の歴史について紹介しましょう。
■縄文後期から人が住んでいた場所

明治10年(1877年)に、モース博士によって発見されたのが「大森貝塚」です。
約4000年~2300年前もの昔、貝塚付近が海岸線に近い場所にあったこと、人々の暮らしがあったことがうかがわれます。
品川区には、「大森貝塚遺跡庭園」があり、歴史的な資料をみることができます。
海と小高い地形が、暮らしやすさを生み、太古の時代から人々が住み着いていた土地であることを考えると、なんだかロマンを感じます。
縄文人ばかりでなく、その後、源頼朝ゆかりの寺社があったことや、明治から大正にかけて文士や芸術家など、文化人が集まる土地柄であったことなど、歴史を紡いできた場所だと言うことがわかります。
関東大震災のあと、地盤が良いことから、文化人が集まってきたためのようです。
JR大森駅の西側は、馬込、山王など、閑静な住宅街としてステイタスのある邸宅街となったのです。
東京ドイツ学校があったことからジャーマン通りと呼ばれる界隈には、洋館などもあり、ハイカラで時代の先端をゆく文化の香りに充ちていたことをうかがわせます。
■海苔問屋・平和島

大森では、古くから海苔の養殖が盛んで海苔問屋が多かった歴史があります。
海苔は1300年前ほどから食べられており、大森は海苔養殖の発祥地です。
ところが、東京湾の埋め立て事業によって、海苔養殖業は姿を消し、今では海苔問屋がわずかに残るだけとなってしまいました。
平和島は、1939年に建設が始まり、太平洋戦争時に工事は中断、捕虜収容所になっていた時代もありました。
1967年竣工し、捕虜収容などの経緯から、平和への願いを込めて「平和島」と名付けられました。
ボート競技場、温泉入浴施設、映画館などアミューズメント施設が集まっています。
平和島は、流通拠点としてトラックターミナルや倉庫も多いエリアとなっています。
■大森周辺の住みやすさは?

海が近くて、京急本線、JRが南北に並行して走っていて、その間には、大型の商業施設がたくさんあり、買い物の利便性がとても高いです。
JR西側のエリアは、邸宅があった広い敷地にマンションが建ち、見晴らしの良い高台に今も閑静な住宅街があります。
羽田空港へも近く、これからも発展が期待される、注目の住宅地なのではないでしょうか。